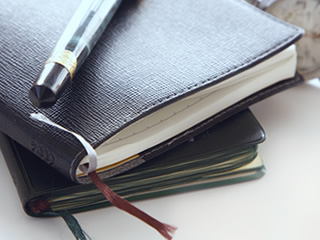|
2025/10/26
|
|
ブランド大でない大学生は、夏休み・春休みを有効活用した資格取得で挽回したい |
|
|
以前書いた、「私が大学生に戻れるとしたら、在学中にどのような資格を取得するか」という記事は、今でも閲覧数が多いです。そこで、具体的にどのように資格を取得するか、シミュレーションしたいと思います。私は就職の専門家ではないので、あくまでも独断と偏見での意見と言うことで、ご了承ください。今は、早くから推薦で進学が決まる場合、高校在学中から資格の勉強を始める人もいるそうですが、ここでは、大学1年の頭、つまり4月頭から資格の勉強をはじめることを想定します。また、これは私の個人的な意見ですが、ブランド大の学生でない者が在学中の資格取得で挽回する場合、資格取得の費用は、自身のアルバイトで賄った方が良いと思います。私もそうしました。親がかりですと、いくら資格を取得しても、勉強しかしていないという印象を与えるからです。資格取得の費用は自分で賄った方が、バイタリティーがあるという意味で、周囲の印象も良いかと思います。今は学生アルバイトの時給も高いですし、少子化で学生アルバイトは引く手あまたですから、融通の利くアルバイトに就くのは、それほど難しくないと思います。そこで、融通の利くアルバイトをし、資格取得の費用は自身で賄うやり方を想定します。夏休み・春休み以外の大学のある時期は、文系なら通学は週4日で済む場合も多いので、大学のある日は2時間半、ない日は、1日はアルバイトをし、残り2日は1日10時間勉強するとします。サークルには入りません。資格取得で這い上がりたいのでしたら、時間がもったいないと思います。 ここでは、大学1年で行政書士に合格して社労士の受験資格を得て、大学2年で社労士に合格することを目標とします。予備校は、フルで何十万円もする本科講座を申し込まず、最初は独学で市販の予備校の教材を使います。4月頭から7月下旬まで、GWもありますし、大学の前期試験の勉強時間を除いても、400~500時間は勉強できますので、独学で一巡できます。そこで、自分は何が苦手で、どこを予備校の講座で補強したいのか、把握します。7月下旬から、予備校の直前講座が始まりますから、必要な範囲で予備校の講座を受講すればよいのです。この方法ですと、予備校の費用は、かなり抑えられます。夏休みは約2か月ありますから、週2日アルバイトをしても、残りは勉強に当てられますので、かなり力を付けられるかと思います。夏休み明けから11月第2週日曜日の行政書士試験まで約1か月半ですが、その期間はアルバイトをせずに、大学以外は試験勉強に専念しても良いと思います。これで、1000時間から1100時間は勉強できますから、法律の知識ゼロから始めても、十分合格可能かと思います。行政書士試験が終わったら、翌年1月第4日曜日の、FP3級を目指します。行政書士試験の相続の知識が行かせますし、2か月半あれば、普通に合格できます。また、年金の知識は社労士に活かせますから、一石二鳥です。 1月下旬に行政書士の合格を確認したら、すぐに社労士の勉強を始めます。こちらも、独学で一巡した後、必要な範囲で直前講座を受講します。8月の第4日曜日の社労士試験まで約7か月ですが、社会人受験生が大半の社労士試験において、大学1年の春休みと大学2年の夏休みを使えるのは、強力なアドバンテージです。大学1年の春休みは週2程度でアルバイトをしても良いですが、7月下旬からの1か月は、試験勉強に専念します。これで、社労士試験まで勉強時間を約1200時間は取れます。FP3級で、年金を僅かながらわかっている、そして、行政書士の合格で、試験慣れして、自分なりの勉強方法を確立した状態でしたら、合格の可能性は十分あるかと思います。また、行政書士の合格で家族から信用を得られれば、社労士の勉強費用は受験後に払う約束で立て替えてもらい、アルバイトをせずに、大学以外は勉強に専念しても良いかもしれません。その場合、より合格に近づくでしょう。 社労士の発表は10月ですが、合格していれば、翌年1月にFP2級(できればAFPも取得)を受けます。年金はFP受験生が苦手とする場合が多いので、社労士の勉強をしていた者にはアドバンテージになるため、ほぼ確実に合格できるでしょう。つまり、大学2年のうちに、社労士、行政書士、FP2級に合格することは、十分可能です。 社労士は、登録に実務経験が2年必要で、それを満たさない場合、事務指定講習が必要です。合格後すぐに申込み、翌年1月下旬から9月までeラーニングを含む講習を受けますが、私でしたら、大学3年からの企業のインターンと並行して、社労士の事務指定講習を受けます。就職して、すぐに社労士登録をすることが可能であることを、就活のアピール材料にするのです。大学3年のインターンの時点で社労士、行政書士、FP2級を取得していれば、ブランド大の学生に対して引け目を感じることもないでしょうし、社労士を取得して、登録のための事務指定講習を受けています、と話せば、俄然、注目されるでしょう。 可能であれば、大学3年の9月にFP1級学科を受け、合格すれば翌年1月にFP1級実技を受験し、合格すれば、就活に更に有利になるかと思います。 内定後、CFPに挑戦しても良いですし、資格はこの辺で一区切り、というのであれば、旅行や、好きなことをやっても良いと思います。 もし、大学2年生以上でこの記事を読んだ学生さんがいらっしゃいましたら、大学院進学を視野に入れて、参考にしていただけたらと思います。 社会人は、職場がその資格取得を推奨していない限り、試験前にせいぜい、2、3日、有給を取得するのが限度でしょう。むしろ繁忙期の場合、1日も有給が取れない可能性があります。その点学生は、夏休み・春休み合わせて、最大で4か月、仮にある程度アルバイトをしても、2、3か月は勉強に当てられますから、強力なアドバンテージとなります。これを生かさない手はないと、私は思います。
|
|
| |