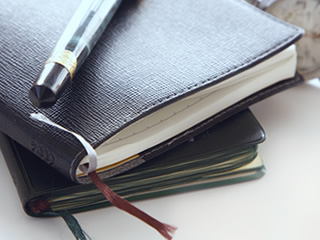|
2025/8/24
|
|
行政書士民法択一の過去問学習についての私見 |
|
|
本年度の行政書士記述式民法の作問が終わりました。私は現在、行政書士の制作の仕事は、記述式民法の作問と、本試験の民法択一の解説を少し書く程度です。講師とは立場が違いますが、記述式民法の作問のため、択一式民法の過去問も研究しています。また、講師だからといって、自分が合格した後の過去問を深く研究しているとは限りません。他校さんの講師のブログの民法択一の過去問についての記事に違和感があったので、あくまで私見ですが、意見を述べてみます。 記事全般を全否定まではしませんが、このフレーズは、エッと思いました。 「過去問に目を通すことに意義がある」 いやいや、目を通す程度じゃダメでしょう、すべて肢単位で正確に正誤を記憶し、最低限の理由付けも正解していないと、土俵にも乗っていないでしょう、と思いました。 確かに、行政書士民法択一過去問は、初めて出題される知識も多いです。それは、出題範囲が広い民法において、僅か9問しか出題されないという、試験の構造的な欠陥にあります。問題数的に行政法の比重が大きすぎますし、一般知識も、もっと比重を減らし、その分、民法の出題数を増やすべきです。私は、最低でも民法の出題は12問が必要だと思います。百歩譲っても、11問にすべきです。 まあ、科目ごとの問題数はすぐには変えられませんが、だからといって、過去問は目を通す程度で良いということには、ならないと思います。民法択一過去問は、繰り返し出題される知識は、たくさんあります。しかも、正解肢が繰り返し出題されています。また、これは酷だろう、という細かすぎる知識も、それほど多くありません。むしろ、酷な出題は、司法書士試験に比べると、ずっと少ないと思います。 また、ほかの記事にも書きましたが、近年の記述式民法の傾向として、択一式の過去の出題論点の記述化が、結構あります。つまり、択一を肢単位で正確に正誤を記憶し、最低限の理由付けも正解できる力があれば、記述式においても、及第点の点数が付く答案が書ける可能性が高いのです。 「過去問をすべて肢単位で正確に正誤を記憶し、最低限の理由付けも正解する。」 最低限、これでギリギリ土俵に乗ることができます(勿論、テキストは過去問以外の知識も一通り読んでいて、特にABランクは読み込んでいるのは前提です)。正誤をすべて記憶するだけではダメです。理由付けを誤ったら、かなり厳しいです。理由付けについては、過去問集の解説に記載のあることを、きっちり答えられる必要はありませんが、少なくとも、核になる部分は答えられる必要があります。 他試験の過去問をやるのは、その後です。それも、予備校がセレクトした問題だけをやるべきです。司法書士試験の過去問集を購入してやりこむなど、完全な自殺行為です。担保物権と身分法は、日本の資格試験では、司法書士試験が最も難しいです。行政書士試験のため、そこまでやる必要はないし、やれば不合格になる可能性は、かなり高くなると思います。予備校関係者であれば、この辺まで言及すべきだと、私は思います。 |
|
| |