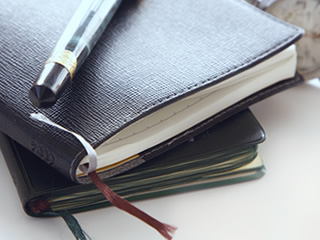|
2025/7/21
|
|
発表待ちの間に時間があるからと学者本を読むのはお勧めしない |
|
|
かなり以前ですが、某塾の本試験1週間後の分析会で、人気講師が「発表待ちの期間に、民法の学者本を読むのも良い。」と話していました。私は、苦笑しながら、「いや~自分は全くお勧めしないけどね。」と思いました。 もう四半世紀前ですが、平成11~15年頃まで、LECの学者本の解説講座がありました。当初は民法と旧商法、後に民訴、憲法も加わりました。民法だけでも24コマもある膨大な講座で、学者の基本書の行間を解説する、濃密で膨大な講座でした。当時はネット普及前で、私は平成11年開講の最初の講義を(翌年民訴も受講)、予備校のビデオブースで視聴していたのですが、講師の解説が濃密過ぎて、ビデオを止めて書きとめて、を繰り返すと、6~8時間ぐらいかかりました。その分、実体法を深く理解できる、素晴らしい講座でした。しかし、それが本試験の点数に反映されたかというと、大して点数は伸びませんでした。 また、10年ほど前、他校さんの、全く別の形式の、深く理解し、思考力を付ける趣旨の講座の、午後マイナーと会社法・商登法を受講しました。こちらも理解が深まる素晴らしい講座でした。でも、同じく、点数の伸びには繋がりませんでした。 これは私の持論ですが、深く理解したところで、それほど点数は伸びません。理解も記憶も、合格最低点が取れる範囲で十分なのです。基礎の基礎が正確に記憶されていれば、ある程度応用問題が解けますし、それで何とか合格最低点は取れます。理解が深まれば、解ける応用問題も増えるかというと、大して増えません。つまり、理解を深める勉強は、費用対効果が悪い勉強とも言えます。 加えて上記2講座は、ボリュームがあり、講義自体が濃密なので、時間を十分に取れる環境にないと直前に回すのが厳しいという、致命的な欠陥がありました。実際、私の知人は、仕事であまり勉強時間が取れない人でしたが、後者の講座を受講した年は落ちて、翌年はその教材は使わずに、もっと絞った講座を受講し、合格しました。この手の講座は、勉強時間がかなり取れる受験生でないと、こなすのは難しいと思います。 それほど勉強時間が取れるわけでもないのに、この手の講座や学者本に手を出してしまい、こなせないと、挫折感も出ます。本試験でピンチの時に、やっぱりもっと時間を取ってきちんと読み込んでおけばよかった、と後悔するなど、マイナス面もあります。 また、法律が大好きな人が、学者本や判例百選に手を出すと、趣味的な勉強に走り、泥沼にはまります。私も泥沼にはまり、そこから抜け出すのに、かなりの年数を要しました。私は、「楽しい法律の勉強」は、特に法律が好きな人ほど、合格するまではしない方が良いと思います。 |
|
| |