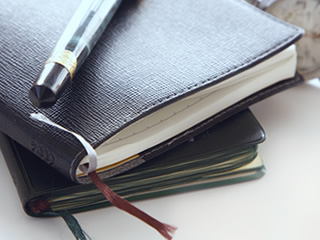|
2025/4/23
|
|
行政書士は基礎がしっかりしていれば普通に合格できる試験 |
|
|
私は、行政書士受験生の9割弱は、基礎が不十分で、やるべきことをやっていないと思っています。このことを、記述式民法をどう得点するかの点から考察してみます。私は、添削をやっていた観点から、記述式民法でどう得点するかは、以下のとおりになると思っています(答案の記載の順序としては、3が2の先です。)。 1 その問題で問われている論点を把握する。 2 問題の誘導に乗って、結論を正解する。 3 理由付けを書く。 1については、行政書士試験の記述式は、複雑な事案から論点を読み取るのではなく、択一式の延長といった程度の事案なので、択一式が合格レベルにあれば、普通にクリアできます。 2については、「問題の誘導に乗る」ということが重要です。つまり、出題者は、何について問うているのか、それに基づいて解答するのです。時折、論点は把握していて、上記1をクリアしていても、問題文が問うていることとは別のことを答えている答案があります。当然、減点となります。行政書士試験研究センターが採点基準を公表していないので、あくまで個人的な推測ですが、ここを誤ると、本試験では、予備校よりも厳しい採点がなされている可能性はあります。ここを誤らないためには、その問いは何を問うているのかの部分について、アンダーラインを引いて、解答を書き始める前に再度そこを読む等で、早合点を防止できるかと思います。また、以前にも書きましたが、論点把握も理由付けもしっかりしているのに、結論を誤っている答案は、結構な数あります。これは、単に詰めが甘いだけです。つまり、基礎の定着が不十分なのです。これも私的見解ですが、本試験では、この点も予備校よりも厳しい採点がなされている可能性はあります。 3については、その問題にもよるので一概には言えませんが、上記1、2をクリアし、理由の主要なキーワードが一つ書けていれば、合格点の6割を取れる場合が多いと思っています。つまり、択一式が合格レベルにあれば、記述式も合格最低ラインの6割を取ることは、難しくないのです。また、理由が模範解答の半分も書けていれば、7,8割の得点が付く場合が多いかと思います。 ところが、以前も書きましたように、公開模試でも、記述式民法が2問とも6割以上取れる答案は、ごく一部です。つまり、大半の受験生が択一式で合格レベルにもなく、やるべきことをやってきていないのです。たとえば、令和4年問46の、賃借権を被保全債権とする妨害排除請求権の債権者代位を難問だとするネットの書き込みを見かけましたが、この論点は平成20年、17年と、択一式で2度も既出です。択一式の過去問を丁寧に潰し、解説をしっかり読んでいれば、6割程度の点数が付く解答は書けたはずです。つまり、この問題を難問だという人は、やるべきことをやってこなかったのです。 行政書士受験生は、9割近くが、やるべきことをやってきていません。択一式で2度も出題された論点を記述式で出題されたら難問と言ったり、理由付けは正解できても結論を誤るような中途半端な知識の定着率だったりすると、やるべきことをやってきたとは言えないのです。ですから、行政書士試験は、基礎をしっかり身に付けるという、やるべきことをしっかりやれば、普通に合格できる試験だと、私は思います。 |
|
| |