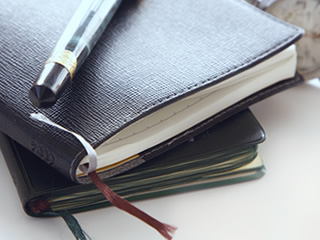|
2025/1/13
|
|
普通失踪と特別失踪の違いを即答できなければ法律家ではない(改訂) |
|
|
教室を持たない某ネット資格予備校がネット広告で、行政書士試験は出題範囲が広い、令和6年は失踪宣告というマイナーな分野が出題された、貴方は普通失踪と特別失踪の違いが即答できますか、という趣旨の問いかけがありました。 いやいや、失踪宣告なんてマイナー分野ではなくて、法律家としては普通に熟知していなければならない分野でしょう、普通失踪と特別失踪の違いなんて即答できなければ、法律家とは呼べないんじゃないですか、と耳を疑いました。そもそも、失踪宣告が成立すれば、死亡したとみなされるのです。失踪宣告の基礎知識がない者に、相続を仕事にする資格はありません。失踪宣告が出たから行政書士試験は出題範囲が広いとか、強い違和感を覚えます。 確かに、行政書士試験において、失踪宣告が単独で1問出題されたのは、令和6年度試験が初めてであり、行政書士試験においては、マイナー分野と言えなくはありません。しかし、肢単位では、総則から令和3年に2肢、平成24年に1肢、相続から平成22年に2肢出題されています。肢単位とはいえ、これだけ多数、しかも近年に2肢出たということは、近い将来、単独で1問出出される可能性があることは、十分予測できたはずです。 行政書士試験は科目ごとの出題数に偏りがあり、民法の択一式9問は少なすぎます。その分、記述式は2問でバランスを取っているのでしょうが、少なくとも一般知識か行政法を1問削って、民法の択一式の出題数を増やすべきだと思います。この点も、受験生が民法の勉強に時間を割かない要因かもしれません。 しかし、出題数が少ないからといって、民法に勉強時間を割かないのはナンセンスです。行政書士試験の民法のテキストは、とても薄いです。上級者であれば、1日あれば精読できる分量です。民法は法律家の心臓部分です。記述式が2問出題されることも考慮し、テキストは精読すべきです。民法の記述式も稀に出題される難問・奇問を除けば、テキストの精読により、合格最低点の6割の答案は書けるはずです。 また、行政書士試験は過去問だけでは対応できないという声もあり、とかく受験生は過去問を軽視しがちですが、何度も繰り返し出題されている知識もあります。現に、令和6年の失踪宣告の出題の正解肢(問題27記述1)は、令和3年の出題の正解肢(問題28記述4)と同じ論点でした。過去問を暗記するまでやっていない者は、落とされても文句は言えません。また、行政書士試験だけでは過去問が薄いことを考慮し、リーダーズ総合研究所・辰巳法律研究所の過去問集では、司法試験や、司法書士試験の過去問を適宜入れています。失踪宣告も、司法書士試験の過去問が1問掲載されています。このように、足りない部分は他資格の過去問で肉付けされている過去問集は有効でしょう(行政書士試験のために、司法書士試験の過去問をすべて解くのはお勧めしません。)。 行政書士試験の予備校の教材は、まあまあ充実しています。予備校の教材を使い、それを反復してものにする、つまり、打つべき手を打てば、普通に結果を出せると思います。現に、令和6年の失踪宣告の問題はとても簡単で、かつ、上記のとおり、令和3年、平成22の出題と正解肢が同じ論点でしたので、過去問を丁寧に潰した受験生にとっては、読んだ瞬間正解できる、秒殺可能なサービス問題でした。失踪宣告の出題が意表を突かれた、対応できなかったというのは、単に打つべき手を打っていなかっただけだと思います。 |
|
| |