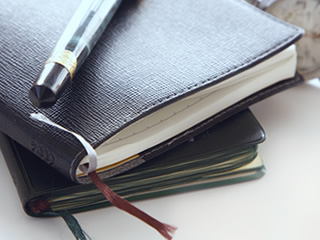|
2025/5/11
|
|
練習でやっていないことは本番ではできない |
|
|
再三、私のブログでは述べていますが、近年の司法書士試験の記述式は、試験時間が同じなのに、平成15年以前試験の倍以上のボリュームがあり、人間の事務処理能力の限界にチャレンジする試験となっています。あくまでも私見ですが、私は、近年の司法書士試験に短期合格する人には、先天的に事務処理能力が高い人が多いのでは、と思っています。現行試験の午後の部には、高度な事務処理能力が求められており、普通の人が現行試験に合格するには、そのための訓練も必要です。これは、平成15年以前の試験には求められていなかった能力です。 では、どうやって高度な事務処理能力を身に付けて現行の司法書士試験の午後の部を乗り切るのか、一つは、書く訓練をし、書く体力を身に付けることです。一昔前の合格者には、記述は普段の学習では、ひな形を暗記するだけで、実際に記述式の問題を解くのは、模試だけだった、とい人がいました(それも問題の相性という名の強運に恵まれた人が多いとは思いますが)。このやり方が通用したのは、せいぜい平成22年頃までです。もしかしたら、平成24年、25年まではギリギリ通用したのかもしれませんが、記述式が不登法6件+小問2問、若しくは7件+小問1問、商登法2問がデフォルトと化した、平成30年を除く平成28年以降の試験では、このやり方では、落とされても文句は言えないと思います。講師や古い合格者に、今では通用しないこの「択一逃げ切り」で合格した者が多いため、今でもこのやり方が通用すると思い、実践し、苦汁をなめている受験生が多いのも、この試験の大きな悲劇だと思います。でも、今はこのやり方は通用しません。模試以外の普段の学習でも、ある程度記述を実際に書いていないと、落とされても文句は言えないと思います。 もう一つの方法は、「判断のスピードを上げる」ことです。「決断を素早くする」と言っても良いかもしれません。試験では、択一式で残り2肢のどちらかに絞り切れないことが、多々あります。記述式で、不登法の申請の順序、商登法の登記できない事項をどうするか、判断がつきかねることがあります。その時、「えいやっ!」と、どちらかに決めなくてはなりません。現行試験の午後の部では、いつまでも考えている時間はないのです。そして、どちらかに決めたら、「本当にその決断で良かったのか?」などと、考えている時間はないのです。 私は、受験晩年は、普段の勉強も、勉強以外の私生活も、「即断即決」を心がけました。そして、一旦決断したら、どんな結果になろうとも、甘んじて受け入れる。決断時も、決断後も、結果が出た後も、自分の決断に責任を持ち、それを受け入れる。とにかく「潔くなる」ことを心がけました。結果、受験勉強も、本試験も、判断のスピードが上がり、うじうじ悩まず、試験に集中し、常に1%でも合格の可能性が高くなる手を打つことができ、結果を出すことができました。 本当は本試験でアクシデントはありました。午前は民法と憲法でそれほど難度が高くないのにうろ覚えの問題があり、正直、2問やらかした、と思いました(実際、やらかしていました)。しかし、基準点は超えている感触はあったので、基準点さえ超えていれば、いくらでも午後に挽回できる、と動揺することもなく、淡々と、午後の試験に挑めました。試験前夜、早く目が覚めて4時間半ほどしか眠っていなかったため、午後は睡眠不足で電池切れとなり、また、当時はコロナ禍のマスク着用で試験を受けていた負担もあり、何度も意識が飛びました。多分、1,2分は眠っていたと思います。令和3年度の午後択一は、史上最低の基準点でしたが、やや難しいという意識はあったものの、特に気にすることもなく、淡々と作業に徹し、結果を出すことができました。 私が本試験で冷静に1%でも合格の可能性が高くなるように冷静な判断ができたのは、普段から即断即決を心がけ、潔くその決断に伴う結果を受け入れていたからです。普段から気持の上がり下がりが激しく、結果を引きずる勉強や生活態度でしたら、冷静に本試験の5時間を乗り切れず、結果を出すことはできなかったでしょう。 人間だからアクシデントがあれば気持ちが乱れるのは当然です。気持の上がり下がりがあるのが人間です。でも、何か大きな目標を成し遂げようと思ったら、特に現行司法書士試験の午後の部のような、人間の事務処理能力の限界にチャレンジするような試験に挑む場合は、普段から気持ちの切り替えを早くする訓練をしていないと、本番ではできないのです。 練習でできないことは、本番でもできないのです。 |
|
| |