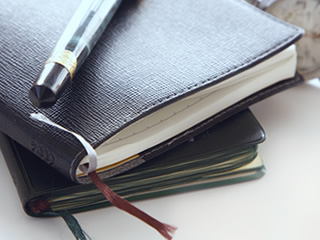|
2025/4/19
|
|
疑問の枝葉を広げる愚かさと、とうの昔から通用しない「択一逃げ切り」 |
|
|
私は、予備校の仕事として、受講生の質問に対する回答を作成していたことがあります。その中で、「この場合はどうでしょう?」と、過去問やテキスト、答練、模試にもない事案を受講生が勝手に作った質問が、3分の1以上は占めていたと思います。 私は、一応、回答は作成しますが、最後に、「疑問の枝葉を広げないように」と、必ず釘を刺していました。そうすると、その約半数の方は、もうそのような質問をしなくなりますが、残り半数は、性懲りもなく、「この場合はどうでしょう?」と、勝手に作った事案の質問を繰り返してきました。 何故、私が、受験生が「この場合はどうでしょう?」と勝手に事案を作って質問してくることを好ましくないと思っているかと言いますと、司法書士試験は最も知識量の多い資格試験と言われており、基礎を身に付けるだけで精一杯で、疑問の枝葉を広げる余裕などないからです。 私が質問に回答した「この場合はどうでしょう?」という事案は、本試験に出るとは思えないものが大半であり、残りは出る可能性が無きにしもあらずではあっても、合否に差の付かない細かなものだからです。つまり、疑問を解消する必要のないものばかりなのです。 たしかに、自分の作った事案に予備校側が回答すれば、より深い勉強をした満足感があります。ほかの受験生に差を付けた気にもなります。でも、合否に差の付かない不要な知識を得ただけですから、純粋に試験の合否という意味においては、何のプラスにもなっていません。むしろ、そんなことに時間と労力を使ってしまい、その間に基礎を繰り返した賢い受験生に、後れを取ったことになります。つまり、退化しただけで、本当は自己満足にすらなっていないのです。 また、近年の試験は記述式のボリューム増により、「択一逃げ切り」が通用しなくなっています。これは別の機会に詳細を書きたいと思っていますが、今の司法書士の受験界の不幸は、講師の世代交代が全く進んでいないため、講師の大半が「択一逃げ切り」で成功した世代の人たちであり、この人たちのやってきたことが、通用しなくなっているのです。平成21年、令和6年と、2度に渡って記述式の配点が増加しましたが、それは、記述式のボリューム増により、減点箇所が増え、減点の点数を付けることが難しくなったからです。平成21年の記述式は不登法の難度が低く、また、平成22年は不登法・商登法のいずれもひな形だけ押さえていれば合格点の取れる、極端に難度が低い年であったため(商登法記述式で役員変更が出なかったのは平成5年、22年だけ)、ギリギリ「択一逃げ切り」で合格することができましたが、平成23年以降、特に平成26年以降は、よほど問題の相性が良くない限り、「択一逃げ切り」は極めて厳しいです。もう10年以上前から、「択一逃げ切り」は、通用しなくなっているのです。 比較的短期間に択一式で高得点が取れるようになっても、記述式でやられて涙を呑む人が話題になったりしますが、それは、今では通用しない「択一逃げ切り」を試みて、記述式の勉強のウエイトが低すぎたからです。ボクシングやサッカーで、攻撃の練習ばかりやって、守備の練習を怠ってきたようなものです。攻撃に破壊力があると華やかでファンも付きますが、守備に難があれば、頂点には立てません。択一式で高得点なのに落ちると、運が悪かった、試験は闇が深い、といった同情票が集まるかもしれませんが、「択一逃げ切り」で合格できた古き良き時代の講師のやり方を妄信して、記述式の勉強が足りなかったのが主な敗因だと思います。択一式では高得点なのに記述式でやられて総合落ちするベテラン受験生の大半が、このパターンだと思います。 記述式の配点が2度に渡って上がった以上、質の伴った記述式の勉強量を増やす必要があります。「この場合はどうでしょう?」などと、疑問の枝葉を広げている余裕はありません。特にフルタイムで働いている受験生が疑問の枝葉を広げるのは、完全に自殺行為だと思ってください。 |
|
| |