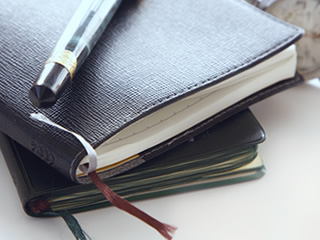|
2025/4/18
|
|
民事信託における司法書士の説明義務違反の判例 |
|
|
KINZAI Financial Planの2025年4月号に掲載されていた、「高齢社会の資産管理」という新連載で、民事信託の組成に関与する専門家の責任について判示された、東京地判令3.9.17が紹介されていました。興味深かったので、更にほかの資料でも調べてみました。 なかなか複雑な事案なのですが、ざっくり説明しますと、将来の認知症対策として、高齢者が委託者兼受益者として、二男を受託者とする信託契約を検討しました。司法書士との間で、信託契約書の案文作成、公正証書手続補助、登記申請代理、信託口口座開設支援等の契約が締結されました。当該信託契約書案文には、信託不動産の維持・保全・修繕又は改良を目的とする、金融機関からの借り入れのための担保設定ができる旨が盛り込まれていました。 しかし、信託登記が実行され、司法書士報酬が支払われたものの、開設された信託口口座は、倒産隔離機能の有する口座ではなく、当時の金融機関は倒産隔離機能のある信託口口座でないと、信託内融資が受けられなかったため、当該事案も、融資が受けられませんでした。そこで、委託者兼受益者が司法書士に対し、損害賠償請求をしたのですが、信託口口座開設については、契約上「サポート」とされており、信託口口座開設を意味するとまでは認定できないとし、その面からの損害賠償責任は認めなかったものの、司法書士が、委任契約締結に先立ち、信託内融資・信託口口座に関する対応状況につき情報を収集し、信託内融資・信託口口座の開設を受けられないリスクがあることを説明すべき信義則上の義務を怠ったとして、裁判所は、司法書士に対する損害賠償責任を認めました。 他人の財産の行く末を左右する仕事である以上、リスクの説明は必須であり、妥当な判決だと思いました。信託については、私も相談を受けることがありますが、対象の財産も報酬も高額であり、慎重にならざるを得ません。本件は、信託組成費用(公正証書作成、登記等)で62万円超、「家族信託組成サポートに係る報酬」として75万円超を受領しており、この高額な費用を考えても、当該司法書士の対応は、杜撰だったように思います。また、当該司法書士は、委任契約締結に先立ち、国家資格でも民間資格でもない、「福祉信託アドバイザー」「福祉信託デザイナー」といった、怪しげな肩書の入った名刺を渡しており、そこまで名乗るなら、リスク説明して当然だよね、という判断をされたようです。私はこのような正式な資格もない肩書を入れるのが嫌いで、そのような行為もハイリスクだな、と思いました。色々と考えさせられる判例でした。 |
|
| |